|
西村医院のあゆみ・トピックス(西村家過去帳等より)
|
|
初代 助善 川崎 蔵人 〜 略 |
領二筑後國上妻郡川崎荘一、住二黒木郷猫尾城一。 |
|
十代 善清 江口傳蔵(後改 竹下) 〜 略 |
永徳二年(1382)、肥前国養父郡江口村。 |
|
|
|
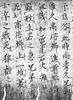 |
天正十二年三月(1584年)、秀久ハ兄惟久ト供ニ隆信卿ノ前ニ進ミ出テ電光石火ノ如クニシテ戦ウモ主君ノ急ヲ救イ難クシテ兄惟久ト供ニ戦死。龍造寺隆信ノ家臣也。
☆ 沖田畷(島原半島)の戦い ☆
天正十二年三月十八日、肥前の熊と恐れられた龍造寺隆信は、島原半島で島津氏に通じて叛旗を翻した有馬晴信を討つため須古の居城を出発し、自ら肥前・筑後の兵三万余を率いて出陣した。同三月二十四日壮絶な戦いの末首を取られ、討ち死にした。
九州戦国合戦記(吉永正春 著)より |
|
二十七代(醫※・初代)
(西村氏祖) |
實久 西村 愈易
|
|
|
 |
故アッテ浪人ヲ致す。(佐賀県)三根郡西村(龍造寺隆信ノ地?)ニ因ミ西村ト氏ヲ改メル。
筑後ノ国三潴郡長門石邑ニ田、宅ヲ買イテ醫※(くすし)ヲ業トスル。
愈易ヲ以テ毉家ノ初代トス。
|
|
|
三十一代(医・七代) |
幸久 西村文啓 |
|
三十二代(医・八代) |
友啓 |
|
三十三代(医・九代) |
猛 |
|
三十四代(医・十代) |
建久
衛 (元院長) |
|
三十五代(医・十一代) |
亮徳(前院長) |
|
三十六代(医・十二代) |
宗胤 (現院長) |
| |
寛(薬剤師) |
| |
(医・十三代)
すみれ
|
|
| 文啓 |
江戸にて医術を修めた。(1878年没、45歳)
1851.5.11,久留米藩吉村辰之丞、大阪勤番中公私日記。 「北村文周弟子西村文啓、御側足軽壱人、勘三郎ニ被属候」
校注 古賀幸雄 より。(当時久留米藩の蔵屋敷−藩主の参勤交代途上の休憩所としても用いられた−に立ち寄り、記帳したもの。)
13/10/2004追記。 |
| 友啓 |
1860年肥前の末次氏に出生、名は郷作。文啓の養子とな
る。1927年没、68歳。
久留米人物誌(篠原正一著)
以上、昭和37年9月19日
久留米市高良山按察使 井上農夫氏 校訂。 |
| 元院長・衛: |
長門石町およびその近郊の住民のため一町医者(全科)に徹
した。
特 に昭和25・6年J.W.ハンター博士(昭和20年終戦後駐留 した米軍 402医学総合研究所寄生虫部長陸軍大佐)の指導を受 けながら、
日 本住血吸虫症(以下、日住症)対策に努めた。
(一時期、昭和10年頃から20年頃まで現在の佐賀県三養基 郡北茂安町東尾に分院を設立)
昭和60年5月12日没。76歳門石町W.ハンター博士(昭和20年終戦後駐留
した米軍
その後、関係者の努力により日住症の予防対策が平成11年には事実上終止符が打たれるようになった。研究所寄生虫部長陸軍大佐)の指導を受
けながら、 日 本住血吸虫症(以下、日住症)対策に努めた。
(一時期、昭和10年頃から20年頃まで現在の佐賀県三養基
郡北茂安町東尾に分院を設立)
昭和60年5月12日没。76歳。 |
| その他
|
伯父の一人が昭和初期頃文豪菊池 寛のマージャン友であったとも聞く。
|
昭和初期からの長門石橋付近の遷り変り
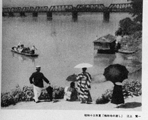 |
昭和13年夏梅林寺の渡し
久留米医師会
江上賢一先生提供 |
 |
昭和30年代の撮影。
現在の長門石橋が架かる前の風景で対岸は梅林寺です。
特に長門石側の湿地地帯には当時危険な宮入貝が見られ、昭和40年前半まで前述の日住症の急性患者さんを診ました。橋が架かるまではこの長門石は陸の孤島と云われていましたが、昭和49年に橋が架かり田園地帯が一大ベットタウンに変身しました。 |
 |
元院長衛、昭和51年4月ハンター博士と20数年振りに再会し、交友をあたためる。 長門石小学校校庭にて |
s
|
|
|
|
|